トップへ
第1日へ
第2日へ
第3日へ
第4日へ
青函トンネル2014 第3日
第3日 2014/06/17. mar.
宿を0930に出発。駅の観光案内所でタクシーの相談をしたら直接交渉して下さいとのこと。小型車に乗りこんで運転士に相談、こういう趣旨で3時間なら貸切りかメーターかどちらが安いだろう? 同じくらいですねえ、貸切りでしたら端数計算ができません、とのこと。メーター制にしました。
まず夢ノートに描いた私案の貨物ルートと新幹線基地の様子を求めて海峡線の七重浜の北方へ歩を移しました。国道227を進み、久根別川を渡り目的地に向かいます。
写真は原則として夢ルートをたどります。特記しないかぎり画面中央がルートの中心線としてお読み下さい。
在来線と新幹線が組み合わさって混乱するので、方向を示すのに札幌方・東京方と標記します。

久根別川右岸堤防から西(東京方)を見る

久根別川右岸堤防から東(札幌方)を見る

上のズーム 国道227と函館江差自動車道のクロス
夢ノートによれば、海峡線を上磯西方から新線として江差自動車道に並行して建設し、函館本線の桔梗駅の南方で両方に分岐して接続します。つまり新線から札幌方面と函館方面に直通できます。
この新線上に函館の貨物設備を全部移して函館貨物ターミナルとします。札幌方面からの貨物列車は方向転換することなく青森方面へ直通できますし、海峡線を青森から来た列車はこのルートを使用して函館へ直通できます。ターミナルから函館方面(有川の貨物駅)への貨物ルートにもなります。
構内が広いので撮影地点を東からABCDと名付けて整理します。
A地点 萩野中央水路の東方340m 自動車道の北150m 未舗装の農道
B地点 萩野中央水路の東方140m 自動車道の北200m 未舗装の農道
C地点 萩野中央水路の西方80m 自動車道の北250m 舗装道路
D地点 萩野中央水路の西方320m 自動車道の北200m 舗装道路

A地点から 東(札幌方)を見る 右は函館江差自動車道

A地点から 西(東京方)を見る ここから向こうへ新幹線の検修庫が拡がります。

A地点から 北を見る
広々とした農地が拡がっています。一面の水田ですがあちこちにビニールハウスがあってなんにもない広さとはイメージが異なります。
農地を見ますと排水路が深く彫り込まれているのに気付きました。水はけに問題があるのなら高めの盛土が必要になります。並行する函館江差自動車道は高架橋ではなく盛土でした。大変な工事量です。
貨物設備の全部移転というのが無理なら当面は信号場として開業し、貨物駅は有川の現在設備、機関車基地は五稜郭北方の現在位置、工場設備は五稜郭隣接の現在位置、貨物の専用線はそのまま残すという流れになりそうです。
北を望めば10kmの彼方、函館平野が尽きるあたりが渡島大野です。2年後に新幹線の新函館北斗駅ができますがいかにも遠い。どの都市でも空港より新幹線駅が都心に近いのが常識ですが、函館空港は市街地に隣接した理想的な位置にあり新幹線駅より都心に近いのです。新幹線は大変不利な選択をしました。

B地点から 西(東京方)を見る 左遠景の樹木が萩野中央水路
これを挟んで東に検修線が 西に収容線が並ぶ配置になります

B地点から 北を見る 車はマイタクシー
 B地点から 東(札幌方)を見る こちらに新幹線の検修庫が位置します
B地点から 東(札幌方)を見る こちらに新幹線の検修庫が位置します
B地点から 南を見る 築堤は自動車道
後述の新函館駅を上磯に置けば新幹線基地もこのあたりになります。適地を求めると貨物ターミナルと隣接することになりました。青森と同じ条件です。
新幹線基地は青森のような折返し基地ではなく、JR北海道の所属車両の基地になるので九州の熊本と同じく総合基地が必要になります。相当大がかりな設備となることでしょう。
また貨物ターミナルは貨物駅と機関車基地と工場を統合しますが、当面は貨物駅は有川の、基地は五稜郭機関区の、工場は五稜郭工場の現状を使用するのもやむを得ないことです。

C地点から東(札幌方)を見る ここには貨物ターミナルが拡がる
このC地点からの西(東京方)は建物があって撮影できませんでした 1軒の農家ですが作業棟や倉庫やガレージが並んでいます

C地点にて 排水溝が深い 水はけが悪いのか
広いところでは距離感が狂います。400mと目測して地図で確認したら倍の800mありました。以後も錯覚に気を付けなければ。 シルクロードの砂漠において戦争で外来者が負けるのは距離感の錯覚が大きな原因だとも聞きました。
タクシー運転士は何のために何をしているのか、興味はあるものの口は出しません。メーターを倒したままなので歓迎しているのかも。

D地点から 東(札幌方)を見る 新幹線の着発線・収容庫が位置する予定です

D地点から西(東京方)を見る

ルート途中 市道から西(東京方)を見る

道道から西(東京方)を見る 向こうは大野川堤防

ルート途中 大野川と戸切地川の間 東(札幌方)を見る

ルート途中 大野川と戸切地川の間 西(東京方)を見る

戸切地川を渡る 西(東京方)を見る

新函館駅の予定地が近くなった 西(東京方)を見る
青い屋根の建物が予定地

北斗市の田園通り 西(東京方)を見る
左はスポーツ公園の野球場 右手に新函館駅予定地
夢ノートの現場検証は説明するのが難しく勝手に先にすすみます。北斗市運動公園の野球場の北側が夢ノート新函館駅です。ちょうどサケマス孵化場があります。
ここから駅前通りが海岸まで伸びて正面に海と函館山が見えるというのが私なりの都市計画です。用地の大半は運動公園の一部移転の跡地です。どんな都市計画が描かれるでしょうか?
現実の新幹線は2年後の開通を控えて姿を現しており、ここから500mの箇所を通過していて高架橋コンクリートの白さが眩しいように輝いています。

手前は田園通り 向こうが駅予定地 青い屋根はサケマス孵化場

上に同じ このあたりが駅前広場になる 遠景は新幹線高架橋

交差点の案内

上の交差点から西(東京方)を見る 正面左はセメント工場

上の交差点から東(札幌方)を見る 青い屋根が駅予定地
スケッチと撮影と感傷の時間を終えて上磯駅に寄りました。別に変哲のない駅ですが有効長のみが長大貨物列車に合わせて改良されています。何となく親しみを覚えて20分ほど構内をウロウロして過ごしました。

駅前の案内図

上磯駅 本屋機能は橋上にある 防寒仕様がものものしい

上磯駅 西寄り構内(青森方面)
海峡線に改築のとき拡張したと思ったら用地はたっぷりあったようだ
島ホームの両側が上下本線 左は行き止りの折り返し線

上磯駅 東方(札幌方)の構内 左2本が上下線 右は折返線

駅前大通りの正面は津軽海峡

海岸に出ると正面に函館山が見える
右は海中に突き出たセメント工場の船積み設備
函館駅前に戻ったらあと50分あります。運転士に函館山に往復できる?と訊いたら昨日と同じく、まかしといて、という返事でした。そのまま駆け足で山に上り、頂上で一回りして引き返しました。
客慣れしているのか要所でちゃんとカメラを持ってくれます。函館山の標高は334m、なんで端数にこだわるの?と質問したら東京タワーより1m高いのです、と。タクシーの支払いは3時間半ほど走り回って¥16000、走行距離を見るのを忘れました。

函館山の頂上から駅を見下ろす 停留されているのは摩周丸
函館運転所構内の広いこと この一部をつぶして函館駅ホームを
直線にできなかったのか?

摩周丸の傍を通りました タクシーのサービスのようてす
残り時間を利用して函館本線で噴火湾に面する森まで行くことにします。これは予定の行動で、私にとっては鉄道で訪れた最北の地になりそうです。基本方針?にのっとりカメラもメモも持たない道中です。
函館1316┄┄(藤代回り、キハ40-1両)┄┄1424森
函館からのローカルはキハ40の1両ワンマン。少し空腹ですが理由があってパン1個を買って乗車しました。。目的はその先なので席でじっとおとなしくしていました。
五稜郭を出た場所にある五稜郭機関区にはEH500とDF200が勢ぞろいしています。場所をブロック分けしてELとDLを分けているのが意外でした。留置は運用第一に考えるのが私たちの常識だからです。検査修繕作業がない以上、混在留置した方が有利です。
市街住宅地域が途切れない七飯までは乗降に活気があります。七飯から運転台直後のお立ち台へ。この線の通称は藤代線。標高130mの大沼へ登るための10‰迂回線です。ローカルは渡島大野と仁山の2駅へ寄るため上り線を逆行するのですがこの列車のみ順路の下り線を走ります。たぶん上り列車が競合して下りが入れないのでしょう。
山腹に這い上がった住宅が線路付近にも拡がり、そのうちに新駅の設置運動が起きるかも知れません。
最後のトンネルを抜けると大沼湖畔ですが、水面から線路まで2mもありません。もし水位が上がったらトンネルが水路となって函館平野を潤す可能性があります。ただし流れ出る川があるので水位が上がることは考えられませんが、勾配緩和のためにぎりぎりのルート選定をしたようです。
大沼は藤代線と砂原線の合流・分岐として複雑な列車体系を受け持っています。ダイヤが過密になったらどうするつもりでしょう。もっともその心配は100年なさそうですが。
初めての方にこの経緯を説明しましょう。
函館本線の七飯~森は南側は仁山経由で、北側は駒ヶ岳経由で単線で開通しました。標高134mの大沼を越えるために両側とも20‰が存在します。
戦時中の貨物輸送の増大に対応して勾配緩和を行うことになり、北側は駒ヶ岳の東側を一周する形で1944年に森~渡島砂原~大沼が開通しました。線区としては最大10‰とすれば目的を達するのですが、この迂回線は最大6‰に抑えました。地形に恵まれたとはいえ大英断だったと言えます。
ここではD52が貨物列車の主役でした。最大勾配区間では貨物列車が20km/hで死闘するのが当時の常識でしたが、6‰ではかなり高い速度となりダイナミックな情景が見られた筈です。もっとも機関車にとっては楽だったかどうか。勾配を少し緩くするからもう少し早く走れというのは却って重労働です。この迂回ルートは通称で砂原線とも呼ばれています。
在来線との分岐は新設された軍川駅となりました。後に駅名の改称があり、軍川→大沼、大沼→大沼公園、となっています。上り列車が名所の大沼を通らないのはまずいとの判断でしょう。
事実上の複線化が完成したわけですが、途中駅は一方通行では困るので逆方向の普通列車が設けられました。現在の普通列車は駒ヶ岳回り(下り線)が6往復、砂原回り(上り線)が6往復です。
また勾配を苦にしない特急気動車は迂回を避けて上りも距離の短い駒ヶ岳経由に移っています。複線化の意義がますます薄れた形です。
一方の南側の勾配緩和はずっと遅れました。貨物列車は上りの輸送量が多かったために、下り列車は空車が多く20‰でも苦労が軽かったのでしょう。七飯~大沼の10‰ルートは1968年に開通しました。通称は藤代線。補機が不要となり、噴火湾に面する短区間急勾配も改良が終わったため、函館~長万部が機関車1両で運転可能となりました。
この南側は山腹に取りついたルートで迂回ではありません。したがって複線として構成され、すべての列車が順方向に運転されます。しかし下り線に位置する2駅、渡島大野と仁山の救済として下り普通列車は原則として旧線(上り線)を経由します。
南区間の普通列車は7往復。そのうち下り2本が藤代線を経由します。理由は不明ですが上り線に列車が詰んで逆行が入る余裕が無いのでしょう。
現在はこういうややこしい列車体系となっています。外から見ると興味津々ですが。
駒ヶ岳の西麓を駆け下りて森に到着。折り返しは21分。まず駅前に出てイカめしの店を探しました。小さい箱で570円。本場での本物です。早速仕入れて駅へ帰りました。ホームは文字どおり海に面していて対岸は室蘭です。海は噴火湾(内浦湾)ですが雨雲のために水平線が見分けられるのみ。

森の駅前広場 中央に立つのは時計台 画面の左手にイカめし本舗


時計台 気温表示があります 森駅の駅舎 入口が住宅の玄関と同じで狭い
のはむろん防寒のため

森駅 上り出発信号機 ここから複線が単線並列となる
直進が駒ヶ岳ルート 車のいる踏切が砂原回りルート
各線の出発信号機は左高位が砂原ルート 右が駒ヶ岳ルート

森駅 長万部方面を見る 右は噴火湾

下り出発信号機 ここから複線となる

上りホームから東を見る(函館方面) 噴火湾の対岸は室蘭の
地球岬のはず 好天の日は見えるのだろうか?

函館方面は2ルートがある
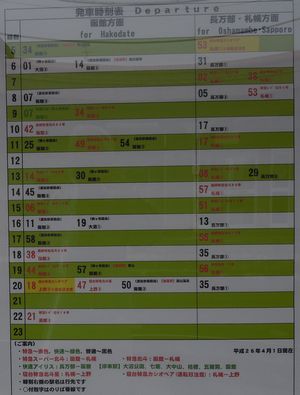
上りは2ルートを混合記入
森には21分の滞在であわただしく帰途に付きました。
森1445┄┄(砂原回り、キハ40-1両)┄┄1611函館
発車の後、まずイカめしを開きます。もちろん飲物も添えて。 ワンマン列車に乗客は6名、まさに貸切り観光列車です。


ここからお目当ての砂原回りの上り線で駒ヶ岳の東側を回って大沼へ登ります。こちらは戦時輸送で効率化(補機の廃止)が求められ1944年に完成しました。戦時中でしたが最優先で施工されたそうです。
地図で見るかぎり海を見下ろしながら次第に高度を挙げて行きます。眼下は噴火湾が拡がる筈なのに当てが外れました。理由は沿線の樹木の繁茂状態です。冬のきびしい土地では植物は短い夏の間に猛烈に伸びます。その沿線の原生林が列車の窓より高く繁れば見晴らしは絶望となります。
原生林とは言葉の綾ではなく人手の入らない自然林の意です。本当に一瞬の切れ目もなく続いてがっくりしました。訪問者の期待を裏切らぬよう雨雲の水平線を隠してくれたのなら、その好意のみを受取ります。

渡島砂原駅 駅前の遠くに海が見える

駅前に人家のない駅が多く、どの駅も車が待っています。3台いると
思ったら降車客も3人でした。

渡島沼尻

鹿部

銚子口
勾配を上り詰めると大沼に再会します。車窓から眺める大沼は神秘さを含んだ湖でいつかゆっくりと再訪したいと願っています。

大沼からの下り勾配は本線である仁山と渡島大野を経由して七飯で
下り線へ合流しました。

仁山のスイッチバック加速線

駅名改称を控えた渡島大野駅

渡島大野駅の傍にある看板
函館駅前は本当にスペースの活用がもうひとつですね。どこへ行くにしても広い駅前広場を横断しないと始まりません。それとここがバスや市電の交通結節点として機能していないと思います。ホテルや企業のビルだけでは新幹線が開通したとき人が寄って来るでしょうか。
もともと連絡船に乗換を考えると現在位置がベストでしたが、今後は都心との便利さと新幹線連絡が重要になります。都市計画で新しい構想が出ても・・・・と思います。
函館1622┄┄(キハ40-2両)┄┄1738木古内
白鳥の出発を待ちながら時刻表をめくると先発の各停が木古内まで逃げきることがわかりました。これを逃がす手はありません。往路と同じく上磯までは近郊線区、以降はガラ空きとなりました。細かい雨のため対岸の津軽半島はまったく見えません。
終着の木古内に到着。江差線のホームでした。海峡線の本線を空けておくためにこちらのホームを残したようです。接続は7分、陸橋をわたって上りホームヘ。きのう親切にしてくれたキオスクのオバサマに折りばらを進呈するヒマはありました。
木古内1745┄┄(白鳥38-6-7A)┄┄1857青森
白鳥の指定席は右側、青森まで指定席におとなしく座っていました。もっとも空席が多いので左右どちらの展望も思いのままです。青函トンネル北海道口は注意していたのにスノーシェッドでわからずじまい。
夢ノートには、新幹線との共用区間で新幹線と在来線の速度差がダイヤの支障原因になるので、共用区間を少しでも短縮すべくトンネルを出てすぐ分岐すべきだと記しています。木古内からの15kmと津軽側の16kmです。共用区間が30km短縮できれば効果は大きいものがあります。
いま気付いたのは双方ともトンネル出口近くに在来線の退避線を設置していることです。北海道側は湯の里信号場(元知内駅)に、津軽側は奥津軽いまべつ駅に工事中でした。これで貨物列車はトンネルを出てすぐ退避が可能になります。夢ノートと同じ発想があり実現しているのは嬉しいことでした。
青森に降りて駅前に立ったとき、一番に思ったのは居酒屋の看板が見える!でした。数えたら居酒屋が7軒、ファミレスが1軒。これなら勝手の解らない初訪問者でも食いはぐれはありません。ともかく日が暮れているので宿へ急ぎました。
ホテルはちょっと場末風の場所。食事か居酒屋の店をを教えて、とフロントの小姐に尋ねたら洋食ですか和食ですか、と返ってきました。和食です。それなら次の路地にある「あじ路」をおすすめします。お客様にはお好みの店だと思います。
のぞいたらカウンター8席、マスター1人のみ。私が最初の客でした。べたついたサービスは全くなし。マスターは聞かれたことの返事しかしゃべらない。次に来たビジネス族と2人で静寂を味わいながら呑み、喰らいました。彼もホテルのフロントでぜひこの店へと勧められた由、マスターはそれを聞いても眉ひとつ動かしません。
昨晩の分まで美味しくよばれて宿に帰りました。
泊 : アパホテル青森駅東
トップへ
第1日へ
第2日へ
第3日へ
第4日へ