宇田賢吉 蒸気気機関車 写真展
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ご案内の写真ハガキ
宇田賢吉 蒸気機関車写真展
と き 2008年5月21日(水)~26日(月)
10:00~18:30 (最終日17:00)
ところ ギャラリーふくふく
福山市今町4-23 (本通り商店街)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
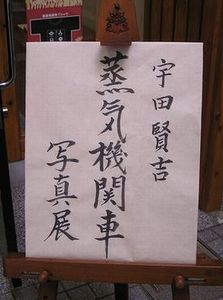
会場の表札 書いてくれたのは小学校の同級生です
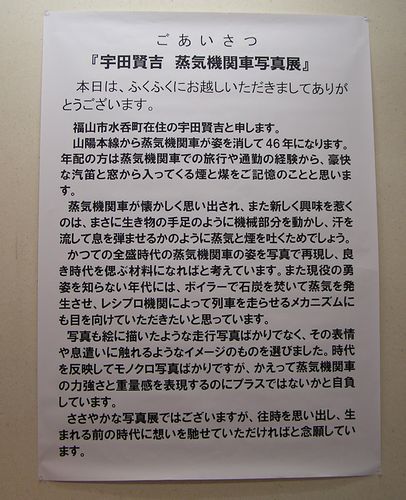
挨拶文

会場は商店街アーケードの中にあります この写真展によって
僅かでも人の流れが増えれば・・・

エントランス 生花はお祝に戴いたもの 正面は記帳台

一歩入ると機関士が出迎えて みんな思わず立ち止
まります
作業服・作業帽・ゴーグル・腕章は私が40年前の現役
時代に使っていたもので汗の跡も生々しいものです。
ボタンはもちろん動輪マークの金ボタン。
首に巻いたタオルは煤煙が入らないようにする必需
品です。第3ボタンの左には時計を入れる小さなポケッ
トがあります
マネキンは同級生のモード店から借りたものですが、
提供者の都合で女性になりました 微妙な体形がおわ
かりですか?
注文すればマリリン・モンローの実物大もあるそうで
す。
写真の配列は変形会場でお客様の動線を意識して決めたものです。したがってテーマ別の配置になっていません。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
眠らないキャブ.

蒸気機関車の運転室をキャブ(cab)と呼びます。夜行列車を運転すると運転室の灯は消えることがありません。
九州の鳥栖発、京都行(福山3:59発)の各駅停車を牽いているC6212号機です。区名の広転は広島運転所(元の広島第二機関区)です。
場所 山陽本線 徳山駅(山口県)
ネガ番号 141002
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
朝の出立

煙突から噴き出す排気は、石炭を燃やした煙とシリンダーで仕事を終えた蒸気の混合したものです。気温の低いときは蒸気が真っ白に広がっ
て、機関車が呼吸する生き物のように感じられます。
場所 山陽本線 広島駅
ネガ番号 073003
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
海の見える転車台

蒸気機関車の向きを変えるときは転車台を使います。長さ20mの鋼鉄製の台が140トンの機関車を載せてゆっくりと回転します。
大きな機関車もお母さんに抱かれた赤ん坊のようです。後ろに光っているのは晴天の瀬戸内海。
場所 山陽本線 糸崎機関区
ネガ番号 081010
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
岡山を発つ「かもめ」

電化前の山陽本線で最も速い列車は特急「かもめ」でした。京都と博多を結ぶ全車指定席の特急で、現在の「のぞみ」や「レールスター」に
相当します。まだ冷房はなく、窓から煙が舞い込んで来ます。
撮影 1961年9月19日
場所 山陽本線 岡山駅西方ネガ番号 056004
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
発機連結

機関車を交換するとき、到着した機関車を着機、出発する機関車を発機と呼びます。
岡山まで電気機関車に牽かれ列車はここから蒸気機関車が担当します。手旗合図に導かれて発機が接近して来ました。
撮影 1961年9月30日
場所 山陽本線 岡山駅
ネガ番号 062013---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
休 息

基地で待機する蒸気機関車の表情です。火は消さないので煙が途切れることはありません。たくましいボイラー、太い煙突、先頭に突き出した
連結器など、パワーあふれる機関車の休息時間です。
撮影 1962年5月25日
場所 山陽本線 糸崎機関区
ネガ番号 090010---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
機上の二人

蒸気機関車の乗務員は、運転する機関士とカマを焚く機関助士の二人です。
真夏も灼熱のボイラーから逃げられません。制服も実用本位の作業服でしたが、ボタンは金ボタンが輝いていました。
撮影 1961年4月24日
場所 山陽本線 糸崎~尾道
ネガ番号 035007---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
任務終了

山陽本線の瀬野~八本松は急勾配があり、重い列車には後部に補機が連結されました。補機とは補助機関車の意味です。
八本松では走行中に補機を切り離します。任務を終えた補機の息づかいが聞こえるようです。
撮影 1963年2月28日
場所 山陽本線 八本松駅
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
特急「さくら」

ブルートレインと呼ばれた寝台列車はいずれも山陽本線東部を深夜に通っていました。
糸崎で電気機関車からバトンタッチした蒸気機関車は下関まで走ります。石炭は大丈夫ですが水は広島と徳山で補給します。
撮影 1962年2月19日
場所 山陽本線 糸崎駅
ネガ番号 080004---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
昼下がりの機関区

我が家である機関区で点検を受けている蒸気機関車です。中央にあるのは給砂塔でボイラーの上にある砂タンクに砂を補給します。砂は空転を
防ぐためにレールに撒くもので滑りやすいレールを走る宿命といえます。
撮影 1961年4月24日
場所 山陽本線 糸崎機関区
ネガ番号 035005---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
運転室からの視界

運転室から前を見るとボイラーが邪魔をするので、これだけしか見えません。煙突に重なって見えている縦長の機器は汽笛で、ボーという太い音色を響かせます。
前方右手に伊勢宮神社の杜が広がります。
撮影 1961年4月24日
場所 山陽本線 松永-備後赤坂
ネガ番号 035014---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
特急 「かもめ」

機関車の次は荷物車、続く3両はグリーン車、その次の大きい窓は食堂車、後に普通車5両が連なっています。
京都を8:30に出発、博多に着くのは18:50
で一日がかりの旅行でした。
撮影 1960年3月23日
場所 山陽本線 本郷-河内
ネガ番号 020006---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
夜明けの機関区

夜行列車の多かった時代には、機関区は夜の方が活気を呈していました。夜明けの光が射し始めるころ、帰って来た蒸気機関車がボイラーの煤
煙を取り出しています。早起きのトンビが一羽舞っていました。
撮影 1962年1月23日
場所 山陽本線 糸崎機関区
ネガ番号 077001---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
連なるけむり

蒸気機関車の牽く貨物列車は連続上り勾配で速度が20km/hまで落ちるので、スピードアップのために補機を連結した列車がありました。
前頭の煙に補機の煙が重なってゆきます。
撮影 1962年5月25日
場所 山陽本線 入野駅西方
ネガ番号 089006---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
横 顔

煙突周りは顔に例えられ、いろいろな形式の機関車が機械美を見せています。
日本で最も優れたデザインだと評されているC59型の横顔です。無理のないバランスの良さが賞賛されています。
撮影 1962年2月9日
場所 山陽本線 糸崎機関区
ネガ番号 079007---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
動 輪

C59型式の動輪直径は175cmあります。あなたの身長と比較してください。
上部に見える34-6-11・TTという標記は定期検査を行った日付と工場を表していて、TTとは鷹取工場のことです。広島工場ならばHSです。
撮影 1962年10月23日
場所 山陽本線 糸崎機関区
ネガ番号 097016---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
疾 駆 細川延夫 賛助出品

鉄道写真の先輩である細川延夫さんの作品です。
機関士席に座っているのは25歳の私です。私の晴れ姿を撮るべく細川さんは仕事を休まれたとのたと、感謝あるのみ。
このC6217は蒸気機関車の日本最高速度記録を持っている名機です。1953年に東海道本線で129km/hを出しました。
現在は東海リニア館に展示されています。入ったエントランスホールにリニア試作車と並んで。
世界の蒸気機関車最高記録は1936年のドイツ国鉄の05型式による200
km/hで、新幹線より28年も前のことです。
撮影 1965年4月11日
場所 山陽本線 三原-本郷
ネガ番号 143001
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
電化前夜

電化工事が進んで駅構内にも架線が張り巡らされました。蒸気機関車の活躍もあと少しの期間です。
水銀灯の照明を浴びた黒い車体の美しさに見とれながらの撮影でした。
撮影 1964年7月7日
場所 山陽本線徳山駅)
ネガ番号 141013
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
磨 く

蒸気機関車は掃除はすべて人手で行うので大変な仕事でした。ボイラーの上は、夏は足元がホットプレートであり冬は寒風にさらされます。
ボイラーの上に輝く安全弁はこのように磨きます。掃除を担当するのは機関士を目指す整備掛の若者たちで、私は1年間頑張りました。
撮影 1960年1月23日
場所 山陽本線 糸崎機関区
ネガ番号 011002---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
修学旅行列車

修学旅行の専用列車がやって来ました。どの窓からも小学生たちの笑顔がこぼれています。行先は宮島あたりでしょうか。
子供たちの喜びを乗せてC59と客車15両は足元の高屋トンネルに吸い込まれて行きました。
撮影 1960年11月25日
場所 山陽本線 白市-入野
ネガ番号 02008---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
トンネルを抜けて

トンネルでは蒸気機関車の煙と蒸気の逃げるところがありません。トンネルから噴き出している煙と蒸気をご覧ください。
乗務員はこの煙と蒸気に包まれて出口が来るまで我慢しています。山腹の白いものは残雪です。
撮影 1963年2月14日
場所 山陽本線 瀬野-八本松
ネガ番号 104001---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
伏見櫓と蒸気機関車
ネガのデータ化の不手際で表示できません
福山駅は1973年に高架となるまで地上を走っていました。
1968年まで、このような蒸気機関車が停車する風景も見られました。機関車は変わっても福山城は昔のままです。
撮影 19●年●月●日
場所 山陽本線 福山
ネガ番号 061●---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
プリンセス ロイヤル
イギリスでは蒸気機関車1両ずつに名前を付けていました。これはプリンセスと呼ばれる形式です。絵の6201はプリンセス ロイヤル。次の6202はプリンセス エリザベスで現在のイギリス女王の名です。6203はプリンセス マーガレットローズ。
この絵は高校の美術の恩師である岩田知治先生から私の結婚祝いにいただきました。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
講評など
中国新聞地域ニュース 運転席から撮ったSL雄姿展
旧国鉄、JR西日本の元運転士、宇田賢吉さん(68)が撮影した蒸気機関車の写真展が26日まで、福山市今町のギャラリー「ふくふく」で開かれている。
宇田さんは1960~2000年に運転士として勤務。運転席から見た蒸気機関車の先頭部分や、積乱雲のように煙と蒸気を吐く列車、直径175センチの国内最大規模の車輪のアップの写真など、現役時代に撮影した1000枚以上の中から21枚を展示した。
農繁期で忙しいのだけど、明日までというので、時間を作って行ってきました。宇田さんは数年前の鉄道誌で乗務記録的な連載をしていて毎月楽しみに読んでいました。書籍化したのがこれ↓
鉄路100万キロ走行記 (単行本)
趣味的な内容であったり、スペック的な事を書いた本は多々あるけど、実際の運転士さんが、運転の事、運転手の思い、それもSL全盛期から、近年のJRまで書いてあるのは、唯一ではないかと思う本でした。しかも、技術的に細かいことまで詳細に書いてあるので感動しました。
今回の写真展でも、SLの写真というだけでなく、ものすごく人やSLの命を感じる写真ばかりでした。行って良かった。
一番印象に残ったのは、SLの安全弁を一生懸命磨いてる若い人の写真かな。ススまみれでキツそうな仕事だけど、SLを手入れしてる誇りを感じました。
宇田さんが丁寧に解説してくれたのだけど、やさしいおじいちゃんって風貌だけど、一言一言が、運転士一筋って重みがありましたね。みんな「懐かしいねぇ」とか言って話してましたけど、オレだけ安全の話とか、整備、機械の話でした(笑)
なにを話しても、まずは「安全」から出てくるのが、すごいな。
新書を出したので早速買ってきました。
電車の運転―運転士が語る鉄道のしくみ (中公新書 1948)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
